JSPO(日本スポーツ協会)におけるスポーツ医・科学の歴史的背景
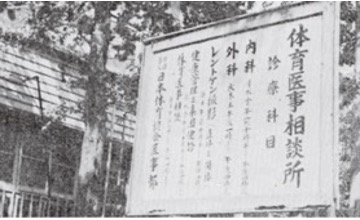
JSPOのスポーツ医・科学の歴史は、昭和22年に「体育医事相談所」を開設し、スポーツ選手の健康管理や医事相談等に着手したことに始まります。その後、昭和34年に1964年東京オリンピックの招致が決定したことから「東京オリンピック選手強化対策本部」がJSPO内に設置されました。昭和35年には「選手強化」に関する研究を推進するため、「スポーツ科学研究委員会」が発足し、昭和36年には「スポーツ科学研究室」が開設され、スポーツ医・科学の情報拠点として各競技団体への「トレーニング・ドクター」の配置や選手強化のサポート活動が行われました。
東京オリンピック終了後、その役目を終えたとして「スポーツ科学研究委員会」は解散することになりました。しかしその7ヶ月後、昭和40年に開催された第7回理事会において「スポーツの振興にとって科学的基盤は必須の条件である」ことから、「スポーツ科学委員会」が設置されるとともに、その所掌部門として「スポーツ科学研究所」と「スポーツ診療所」が開設され、引き続き「競技力向上」、「選手強化」に関する研究が行われました。また、これらのノウハウを全国に広げていくため、「競技力向上委員会」の設置やスポーツ指導者養成事業を支援しました。 昭和50年以降、「競技力向上」、「選手強化」に関する研究に加え、「国民スポーツの振興」のための研究が展開されました。
平成13年には国立スポーツ科学センター(JISS)が開設されたことを受け、「競技力向上」、「選手強化」は主にJISSが担うことになりました。同年、「スポーツ診療所」が廃止され、平成14年には「スポーツ科学研究所」が「スポーツ科学研究室」に改称されました。
その後現在に至るまで、スポーツ医学、運動生理学、心理学、社会学などの様々な

研究領域から、わが国におけるスポーツを推進し、誰もが安心・安全なスポーツ環境を構築すべく、医・科学研究プロジェクトを展開しています。
令和3年には、「スポーツ科学研究室」が文部科学省から科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)第2条第1項第4号に規定する研究機関に指定されています。
わが国におけるスポーツ推進のための医・科学研究プロジェクト
わが国におけるスポーツに関するニーズが多様化し、また総合型地域スポーツクラブの育成や地域の活動拠点となる広域スポーツセンターの設置が推進される中で、21世紀におけるスポーツ推進の新しい形を模索するための「スポーツ医・科学研究プロジェクト」を積極的に展開しています。
国民スポーツ大会については、都道府県スポーツ協会と連携を保ちながら、選手・指導者に対する医・科学サポートを推進してきています。2003年静岡国体から始まった国スポにおけるドーピングコントロールをきっかけとして、全国的なアンチ・ドーピング普及・啓発活動を推進し、様々な情報の提供に努めてきています。
また、スポーツ指導者の資質向上のため、医・科学研究プロジェクトの実践を通して最新の情報を提供するとともに、指導者養成の実態に合わせた知識や技能を提供するための様々な資料を作成しています。特にジュニア層の育成に関しては、子どもが楽しみながら積極的にからだを動かすとともに、発達段階に応じて身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラム「アクティブ・チャイルド・プログラム(JSPO-ACP)」を制作し、普及・啓発を進めています。
さらに近年は、これまでの活動を継続しつつ、性的指向および性自認等の多様な性のあり方や、暴力、虐待および差別等の人権侵害防止に関する調査を行うとともに啓発活動を行うプロジェクト「体育・スポーツにおける人権侵害防止に関する調査研究」、気候変動および生物多様性の損失への対応を主とした環境保護の視点からスポーツの持続可能性の推進に資する基礎資料を提示するとともに啓発活動を行うプロジェクト「環境保護の視点からみるスポーツの持続可能性に関する調査研究」を設置しました。
スポーツ医・科学研究プロジェクトの詳細やその成果については、研究報告書、各種ガイドブックやVTRなどにまとめられておりますので是非ご活用下さい。
※現在行われているスポーツ医・科学研究プロジェクトの概要については、こちらに掲載しています。
スポーツ医・科学委員会 委員一覧(令和7年6月25日現在)
スポーツ科学研究室 研究職員一覧(令和7年4月1日現在)
競争的外部資金 採択課題一覧(令和7年4月1日現在)
○ 採択課題一覧
 (48KB)
(48KB)